ニューロダイバーシティって何?“生きづらさ”を“個性”に変える視点とは
最近、「発達障がいが増えている」というような話を耳にすることが多くなってきましたよね。実は、発達障がいが増えたわけではなく、その言葉が広く使われるようになったのは2005年以降とわりとつい最近の話で、発達障害支援法という言葉が法的に定義されて以降、医療現場などで正式に使われるようになりました。
心理カウンセリングを行っていると、「自分はADHDかもしれない」「グレーゾーンと言われたけれど…」といったお話をされる方がよくお見えになります。診断の有無に関わらず、「生きづらさ」や「他者との関わりが難しい」と感じている方は非常に多くいらっしゃいます。
今回は、そのような生きづらさを“欠陥”ではなく“個性”として見直す考え方──ニューロダイバーシティについて、ご紹介したいと思います。
ニューロダイバーシティとはなにか?
「neuro=神経」「diversity=多様性」という言葉の通り、人間の脳や神経のあり方は多様である、という考え方です。
ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD、学習障害(LD)、トゥレット症候群など、従来“障害”とされてきた特性を「脳の違い」として捉え、それを病気として“治す”のではなく、「共に生きるためにどのような環境調整ができるか」を重視します。
ラベルが人を苦しめることもある
診断名がついて安心される方もいらっしゃいます。自身の困りごとに名前がつくことで、自己理解や対処がしやすくなるという利点もあります。
しかし一方で、「発達障がい」というラベルが、周囲からの偏見や過剰な干渉を招き、むしろ生きづらさを強めてしまうケースも少なくありません。ラベルがついてしまったせいで、そのラベルに苦しんでしまう方も多く存在するのではないでしょうか?
実際に、「発達障害と診断されてから親が過干渉になった」「職場で配慮という名のもとに業務を制限され、疎外感を覚えた」といったお声もよく耳にします。
社会が変わるという視点
ニューロダイバーシティの重要なポイントは、「本人が社会に合わせる」のではなく、「社会のほうが多様性を受け入れる」という姿勢にあります。それは、腫れ物に触るようなかかわり方をするということではなく、違いをふんわりと受け止めて共存するという考え方です。
ユニバーサルデザインや合理的配慮といった概念にもつながりますが、これらは特定の人のためというより、「すべての人にとって過ごしやすい社会を目指す」ための取り組みです。
例えば、「騒がしい環境では集中できない」という特性は、多かれ少なかれ誰にでもあるのではないでしょうか。その「度合い」が異なるだけで、本来は優劣をつけるものではありません。
私自身の体験と重なる部分
私自身、セクシャルマイノリティとして生きてきた中で、周囲からの価値観の押し付けや「こうあるべき」という枠組みに生きづらさを感じてきました。自身の個性をラベリングしてしまった途端、周囲から向けられる目が変わってしまったという経験、私にもあります。
その経験があるからこそ、「違い」を“矯正すべきもの”と見るのではなく、“ありのまま受け止めること”の大切さを、実感として持っています。
ニューロダイバーシティという考え方には、そのような視点と深い親和性を感じています。
カウンセラーとして感じること
私自身も以前は、特定のクライアントさんに発達障がいの診断がついているかどうかを意識して対応していた時期がありましたが、決してそれだけにとらわれていたわけではありません。
しかし現在では、診断名よりも「その方が今、どのような困難を抱え、どのように生きていきたいのか」という点を大切にしています。発達障がいという言葉そのものよりも、その方自身が今後どのように生きて行きたいのか、その方自身の価値観を大事にし、お話に向き合っています。
ここが結構重要なのですが、困りごとがないのであれば診断名は必ずしも必要ではありません。逆に、困りごとがあるのであれば、診断の有無に関係なく、支援や配慮は必要です。
また、いわゆる「違い」があるからこそ発揮される強みも確かに存在します。ADHDの方の行動力、ASDの方の集中力や探究心など、いずれも周囲に新たな価値をもたらしてくれるものです。
普通って何だろう?
「普通とは何か」について、私たちは改めて考える必要があるのかもしれません。
学校や会社など、多くの場面で「多数派」が暗黙のうちに“正解”とされることがありますが、それに当てはまらないからといって“間違い”であるとは限りません。
生きづらさに名前をつけることで、少し自分を理解できるようになった。そんな体験が、これからの人生を少しだけ軽くしてくれるかもしれません。
違いは個性、あなたはあなたらしく。ニューロダイバーシティという考え方が、その一助になれば幸いです。

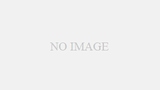
コメント